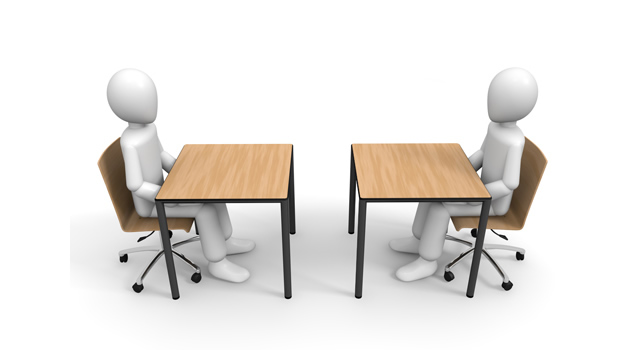実技試験の構成と点数配分
実技試験は「論述」と「面接」から構成され、150点満点、点数配分は論述50点、面接100点で、合計で6割の90点以上が合格ラインとなっています。
論述の方が得点をとりやすく、合格を目指すうえで論述で得点を稼ぐことがポイントとなります。論述で30点より超過した分は後半の面接実技の貯金となります。30点台の後半を目指し40点超えであればなお良いと思います。
【試験結果】
以下は17回~24回の試験結果です。
【JCDA】
| 回数 | 学科 | 論述 | 面接 | 同時合格率 | 実技合格率 |
| 点 | 点 | 点 | % | % | |
| 17 | 70.2 | 31.1 | 60.9 | 46.5 | 59.4 |
| 18 | 77.0 | 30.9 | 60.5 | 54.6 | 57.0 |
| 19 | 71.7 | 32.7 | 60.9 | 52.5 | 63.3 |
| 20 | 75.1 | 33.2 | 61.0 | 60.7 | 64.4 |
| 21 | 71.2 | 32.6 | 60.4 | 52.8 | 62.9 |
| 22 | 77.6 | 33.1 | 59.9 | 59.3 | 65.3 |
| 23 | 76.9 | 32.4 | 60.8 | 59.8 | 62.5 |
| 24 | 68.6 | 33.0 | 60.6 | 45.8 | 64.5 |
| 単純平均 | 73.5 | 32.3 | 60.6 | 53.9 | 62.4 |
【キャリ協】
| 回数 | 学科 | 論述 | 面接 | 同時合格率 | 実技合格率 |
| 点 | 点 | 点 | % | % | |
| 17 | 69.8 | 30.3 | 60.9 | 40.7 | 57.0 |
| 18 | 77.3 | 32.5 | 61.3 | 64.0 | 68.0 |
| 19 | 70.8 | 30.9 | 61.1 | 46.1 | 59.7 |
| 20 | 74.9 | 30.7 | 60.8 | 51.0 | 57.5 |
| 21 | 71.6 | 30.3 | 60.4 | 43.9 | 54.9 |
| 22 | 77.8 | 32.8 | 60.5 | 59.3 | 63.2 |
| 23 | 77.6 | 32.0 | 60.7 | 61.2 | 63.3 |
| 24 | 68.9 | 32.6 | 60.6 | 45.2 | 65.8 |
| 単純平均 | 73.5 | 31.4 | 60.7 | 51.4 | 61.1 |
17回以降の結果を見ると、①学科は両団体ともに得点がアップダウンをくり返しており、それが同時合格率の変動に影響を与えている。②面接実技はJCDAの22回を除き60点以上で安定しており、振れ幅(最高平均点-最低平均点)もJCDAが1.1点、キャリ協が0.8点となっている。③論述は平均は30点以上となっているが、6回分の単純平均はJCDA32.2点、キャリ協31.2点、振れ幅がJCDA2.3点、キャリ協2.5点となっている。④同時合格率は50%を下回った回数はJCDA1回、キャリ協3回となっており、数値の変動がキャリ協の方が大きい。キャリ協の合格率が高い回は論述の特点が高いことがその要因として考えらます。
【論述について】
論述の設問と点数配分の相違
以下両団体の論述の設問です。
【JCDA】
| 項番 | 内 容 | 点数 |
| 1 | 指定語句による面接ケースの比較 | 15点 |
| 2 | CCのやりとりの適切性の評価と根拠 | 10点 |
| 3 | CCから見たCLの問題点 | 15点 |
| 4 | 相談者像を前提とした面談の展開 | 10点 |
【キャリ協】
| 項番 | 内 容 | 点数 |
| 1 | 相談の概要 | 10点 |
| 2 | CCの意図 | 10点 |
| 3 | 相談者の問題点と根拠 | 20点 |
| 4 | 今後の面談の進め方の方針 | 10点 |
両団体の論述の特徴
【JCDA】
問い1・2はCCの「面接のやりとりの適切性」を評価し論じるものでJCDAの特徴となっています。
受験生のなかには設問1の「指定語句」に苦手意識を感じている方もおいでになりますが、問い1・2の解答方法にはいくつかの抑えるべきポイントがあり、ポイントを習得すると比較的安定した得点をあげられることになり得点源となりえます。
15回以降、逐語の文章量が増え2ページとなりました。また、16回から配点が変更され、問い2が15点→10点、問い3が10点→15点となり、加えて、問い3の解答欄が1行増加しました。問題点のとらえ方により配点10点の問い4も影響されるためCLの問題点を指摘する問い3の解答がより重要になりました。
逐語の文章量と解答欄の多さを勘案すると問題の読み解きと文章作成にスビードがより求められるようになったと思います。「時間との戦い」ですね。
【キャリ協】
15回から「逐語形式」から「事例記録形式」へ変更されました。設問1は「相談の概要」を問うもので転機となった事柄、感情を含めて主訴(CLが訴えたい問題)を書くことになります。設問2は「CCの意図」について問われる質問ですが、これらの問題は書きづらさを感じる方もいますので、答練のなかで書き方をマスターして要約能力を高めておくことが必要です。
設問3で「問題点」「根拠」に各10点で計20点配分されていることと、問題点のとらえ方により配点10点の設問4も影響されるためキャリ協においても設問3が重要です。
事例記録の文章量と解答欄が15行と少ないことを勘案するとJCDAに比較して、量的には負担が少ないと思いますが、限られた解答欄で内容を整理し必要なことを簡潔に書けることが求められるため、より深い考察と文章力が求められると思います。
解答作成時の時間配分について
最近は、手書きに不慣れの方も多く、試験においてその点で意外と苦労される方がおいでになります。書く速度や文字の大きさなどに個人差があり、答練の段階から手書きで解答を作成するとともに、自分に適した解答作成までの読み解きの時間と解答作成時間の配分、問題を解く順番を検証しておくことが必要です。
☞両団体ともに論述問題をより多く解き適切な添削とアドバイスを受けることが必要です。 当方のレッスンでは毎回課題を提供し解答を作成していただき添削し答練を重ねます。
面接について
面接のポイントと口頭試問の大切さ
面接実技試験は「ロープレ」と「口頭試問」から構成されています。ロープレでは関係構築を意識し、CLの主訴、問題点の把握することが求められます。CLに丁寧に話を聞いてもらっていると感じてもらえるか、そのためにはあいづち、うなづき、伝え返しなどを組み合わせながら面接を進められるよう反復練習が必要です。単調にならないよう、抑揚、強弱をつけることや間のとり方もポイントです。関係構築が進まなければCLの話す内容が限られ、主訴や問題点の把握にも影響が生じると思います。
もう一つのポイントは口頭試問です。ロープレの良し悪しはもちろん重要ですが、仮に、ロープレが不満足な結果となったとしても口頭試問で適切に回答することができれば挽回も可能でと考えられます。最後まであきらめず冷静に口頭試問に対応することが肝要です。
口頭試問の内容と相違点
以下が両団体の口頭試問の内容です。

設問4・5のCLの問題点と今後の面談の展開は共通しており、論述にも同様の設問があります。この設問に的確に回答するためにはCLの問題点の見立てがポイントとなります。JCDAでは問題点を単独で聞かれずいきなり今後の面談の展開を聞かれることが多くなっています。第20回からはキャリ協においてもできたこと・できなかったことの後、主訴・問題点を聞かれず、今後の面談の展開をいきなり聞かれるようになりました。この場合、問題点の見立てにふれつつ今後の対応について回答すればよいと思います。
問題点を論じるためにはその根拠を明らかにする必要があります。論述は「文字情報」から、面接は「CLの言語と非言語(ノンバーバル)」から見立てることになります。口頭試問は直前に実施したロ―プレのやりとりを自分の記憶を頼りに行わなければならないため、とても高度なことを求められていますので最初はとても難しく感じます。そのためにはロープレ・口頭試問の反復練習と適切なアドバイスが必要と考えられます。
また、論述の答練を重ねることにより「問題点の根拠となる部分のとらえ方」「CLの問題点」「その問題に対する面接の展開」について理解が深まり、論述の解答作成力が向上するとともに。それはロープレと口頭試問の設問4・5の対応力も高めることになります。
面接の練習ポイント
ロープレが思うようにできずに悩まれる方も多いと思いますが、課題は各々違いますしご自身の課題を適切に把握することが必要です。例えば、以下のようなケースが見られます。
・15分の面談を維持できず途中でストップしてしまう
・同じような内容のやりとりの繰り返しになってしまう
・事柄中心のやりとりになり感情が聞けない
・やりとりに窮して「要約めいた」ものを行いCCが長々と話してしまい結果、閉じた質問になってしまう
・やりとりに窮して「提案・気づき」に向かうやりとりをするがCLから拒否される
・ロープレの内容が記憶に残らない※ので口頭試問がうまくいかない
※記憶に残らないと訴えられる方がおいでになりますが、その原因は伝え返しや次の質問に意識がいっており実際にはCLの話を十分聞けておらず内容を理解していないと思います。CLの話に集中し、理解することが何よりも大切です。
様々な講習会や練習会でのフィードバックは、「時間が短い」「内容が抽象的」「問題点を指摘するだけ」「録音を聞き返してと言われるだけ」など、適切なアドバイスやフォローがなされていないとの感想をもらす受験生も多くいますし、受験生同士ですと限界があると思います。
☞当レッスンではCLの問題点を明確に設定した資格保有者と毎回違うケースのロープレを行います。適切なフィードバックを受けることが効果的な練習になると考えられますので、「ロープレ終了後のフィードバック」に加えて、当方指定のシートを利用してセルフチェックしていただいものに当方から追加コメントし、フィートバックを重層的に実施します。
参加者の進捗状況や課題は各々違います。課題とその改善状況を踏まえ、レッスンを繰り返すことにより実技の対応力が高まるようサポートしていきますので、一緒に学びたい方のご参加をお待ちしております。